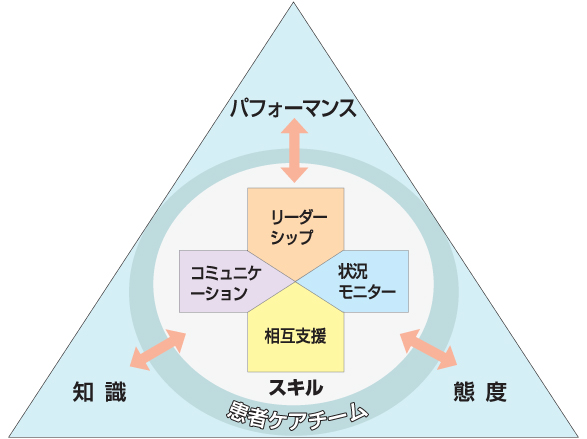1. SAMPLE:JATECのsecondary surveyにおける病歴の聴取
- Signs and Symptoms: 症状は?
- Allergies: 薬や食べ物のアレルギーは?アスピリン喘息は?
- Medications: 処方薬、OTC薬、置き薬、サプリ、通販薬、合法ドラッグ、麻薬
- Past History, Pregnancy, Perinatal period: 過去に同様なことは?既往歴は?妊娠、授乳は?
- Last Oral Intake: 最後に何をいつ口に入れた?
- Events Leading up to Illness/Injury: どうしてこんなことに?思い当たることは?
説明モデルとは、病いに対する解釈の枠組みのことで、医療者と患者では内容は異なっても、その枠組は共通している。そして、患者のそれを知ることは、Narrative-Based Medicineそのものと言える。詳細は、医療人類学の泰斗Arthur Kleinman氏の論文[1]や和訳されている上掲書に詳しい。
- Label どんな病気?
- Etiology 病気の原因は?
- Timing 病気になった時期は?
- Severity どのくらい重い?
- History どういう経過でこれからどうなりそう?
- Effect 心身に与える直接的な影響、症状とか心理的反応。
- Affect 上記により二次的にQOLに与える影響。家事、仕事に及ぼす影響。
- Remedy どういう対処をしてこれからどういう治療を希望するか?
- Aggravating and Alleviating Factors 憎悪・緩和因子
- Severity 程度
- Quality 性状
- Location 部位
- Associated Symptoms 随伴症状
- Setting 開始
- Timing 経過
研修医の先生が別な覚え方を披露をしてくれた。
- 急性か慢性か
- 性状
- はきけをはじめとする随伴症状
- ラジエーション、放散を含めた部位
- いんし、症状を増悪あるいは改善させるもの。
- タイムコース
特に痛みの性状に関しては、方言や言語により違いがあることに配慮が必要である。津軽弁に関しては、青森民医連で津軽弁講座が開かれていたり、データベースが作られたりという取り組みがある。英語の場合、McGill Pain Questionnaire[2]というものがある。下記のリストで自分の痛みを表す語を各群で1つのみ選択し、丸で囲む。1~11群で選んだものを3語、11~15群で選んだものを2語、16群で選んだものを1語、17~20群で選んだものを1語に絞り、定量化するという方法である。
1群 (temporal): Flickering(1), Pulsing(2), Quivering(3), Throbbing(4), Beating(5), Pounding(6)【参考文献】
2群(spatial): Jumping(1), Flashing(2), Shooting(3)
3群(punctate pressure): Pricking(1), Boring(2), Drilling(3), Stabbing(4)
4群(incisive pressure): Sharp(1), Cutting(2), Lacerating(3)
5群(constrictive pressure): Pinching(1), Pressing(2), Gnawing(3), Cramping(4), Crushing(5)
6群(traction pressure): Tugging(1), Pulling(2), Wrenching(3)
7群(thermal): Hot(1), Burning(2), Scalding(3), Searing(4)
8群(brightness): Tingling(1), Itchy(2), Smarting(3), Stinging(4)
9群(dullness): Dull(1), Sore(2), Hurting(3), Aching(4), Heavy(5)
10群(sensory miscellaneous): Tender(1), Taut(2), Rasping(3), Splitting(4)
11群(tension): Tiring(1), Exhausting(2)
12群(autonomic): Sickening(1), Suffocating(2)
13群(fear): Fearful(1), Frightful(2), Terrifying(3)
14群(pinishment): Punishing(1), Grueling(2), Cruel(3), Vicious(4), Killing(5)
15群(affective-evaluative-sensory: miscellaneous): Wretched(1), Binding(2)
16群(evaluative): Annoying(1), Troublesome(2), Miserable(3), Intense(4), Unbearable(5)
17群(sensory: miscellaneous): Spreading(1), Radiating(2), Penetrating(3), Piercing(4)
18群(sensory: miscellaneous): Tight(1), Numb(2), Squeezing(3), Drawing(4), Tearing(5)
19群(sensory): Cool(1), Cold(2), Freezing(3)
20群(affective-evaluative: miscellaneous): Nagging(1), Nauseating(2), Agonizing(3), Dreadful(4), Torturing(5)
[1] Arthur Kleinman. Culture, Illness, and Care: Clinical Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research Ann Intern Med February 1, 1978 88:251-258.
[2] Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain. 1975 Sep;1(3):277-99.
[2] Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain. 1975 Sep;1(3):277-99.